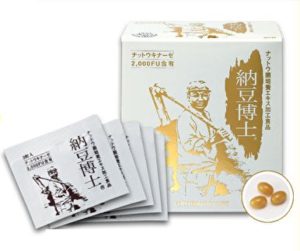
今回ご紹介するのは、販売18年目のナットウキナーゼのパイオニア的存在、「納豆博士」です。
・血栓症とは
・血栓症は、35歳以上から特に注意が必要です
・日頃の生活習慣が大切です
・納豆博士をお勧めする5つの理由
血栓症とは
血栓症(けっせんしょう)とは、血管内に血栓ができ、血液の流れが滞ってしまう状態です。血管が傷付くとと、失血を防ぐために血小板の塊ができます。血管が傷害されていない場合でも、血液がドロドロの状態では血塊が形成されます。もしこの凝固の程度が激しいと、凝血塊は形成された血管内皮から遊離し、血管内を流れて、血管が細くなった所に留まってしまい、血流に影響を与えてしまいしまいます。
血管内腔の面積の75%以上を血栓が占めると、組織に供給される血流が低下し、その結果酸素供給の低下と代謝産物である乳酸の蓄積に伴う症状が現れる。さらに内腔の90%以上が閉塞すると完全な酸素喪失状態になり、その結果、末梢臓器の細胞が死ぬことを梗塞と言い、血栓が詰まる場所により、脳梗塞や心筋梗塞と分類されます。飛行機に乗っている際、狭い機内で長時間同じ姿勢でいることによって起こる深部静脈血栓症(エコノミークラス症候群)も血栓症の一つです。
血栓症は、35歳以上から特に注意が必要です
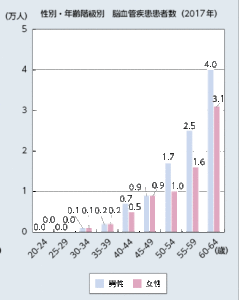
この血栓症は、35歳以上の方は特に注意が必要です。厚生労働省患者調査によると、35歳以上から発症者数が急増しています。
また、現在、日本人の死因の第1位はがんですが、第2位は心筋梗塞などの心疾患、第3位は脳梗塞などの脳血管疾患になっています。つまり、日本人の約3割が 「血管がつまる・破裂する」ことにより死亡しているのです。
【納豆博士】公式ホームページ
![]()
日頃の生活習慣が大切です
最近では、食生活や生活習慣の変化により、若年層であっても、血液成分のバランスが崩れ、高コレステロールや中性脂肪の多いドロドロ血液の方が、とても増えています。不健康な食生活、運動不足、そしてストレスなどが原因で、血栓を溶かす体の働きが弱まり、増々、血液中に、血栓ができやすくなってしまうのです。そして、自覚することなく、それらの症状は進んでいくのです。
心筋梗塞や脳梗塞は、血液中にできた血栓が血管を詰まらせることにより引きおこされる病気です。血栓症は、多くの場合、自覚症状の無いまま突然発症します。
ある日突然襲ってくる血栓症に対し、何よりも大切なのが「予防」です。血栓を作らず、できてしまった血栓を溶かす体質になるためには、運動や食事による生活習慣の改善が必要です。
納豆博士をお勧めする5つの理由
長年、身に付いた生活習慣を、急に変えることは、なかなか難しいものです。そこで、お勧めするのが、安心&安全なナットウキナーゼを豊富に含んだ「納豆博士」です。
「納豆博士」は2002年3月の発売以来、今年で19年目を迎えるベストセラー健康食品。そして、健康の維持はもちろん、ドロドロ生活が気になる多くの方々にご愛飲いただいています。そして、「納豆博士」が多くの方の支持を得ているのには、しっかりとした理由があります。
理由①:ナットウキナーゼは活性度が重要です。
ナットウキナーゼの摂取したい必要量の目安は、2,000FUです。FUとは、「フィブリン分解ユニット」の略称で、ナットウキナーゼの『活性度』を示す単位です。ナットウキナーゼの「元気の良さ」を表す大切な指標です。実は、ナットウキナーゼの活性は、時間の経過とともに、次第に低下してしまうのです。「納豆博士」は賞味期限の2年間にわたり2,000FUの活性を確保するため、製造時には約10%をオーバーする2,200~2,300FUの規格で製造しています。賞味期限内は、いつでも安心の必要量を摂取できるようにしているのです。
理由②:ナットウキナーゼという酵素は「熱」や「酸」に弱いのです
ナットウキナーゼという酵素は「熱」に弱いのです。納豆を加熱料理したりすると、その働きはほ、とんど消えてしまいます。また、「酸」にも弱いので、納豆をそのまま食べても胃酸に触れておよそ半分が死滅してしまいます。
そのようなナットウキナーゼの弱点を克服するため、「納豆博士」は、成分をソフトカプセルで包み込み胃酸の影響を低減して腸まで届くように作られています。さらに、保管時も1日分3粒ずつの個包装になっているので、酸素にも触れにくく、品質を保持しているので安心です。
理由③:お薬との飲み合わせも安心です
「納豆博士」はビタミンK2を完全に除去したサプリメントです。その理由は、ワーファリンなどの、お薬との飲み合わせを考えています。ドロドロ生活で重い病気に罹ったことのある方は、他のお薬との飲み合わせを考慮する必要があります。ワーファリンなど、血液をサラサラにするお薬を処方される場合、お医者さまから納豆を食べないように指導されることがあります。それは、納豆にはビタミンK2が含まれていることが原因です。「納豆博士」は独自製法で納豆に含まれているビタミンK2を完全除去しているので、お薬との飲み合わせも安心してお飲むことができます。「納豆博士」はナットウキナーゼだけをシンプルに配合するという規格で製造されています。
また、大豆だけでなく、すべての原材料において、遺伝子組換え原料を一切使用していません!
理由④:栄養食品協会の厳しい検査を受けています。
「納豆博士」は、公益財団法人日本健康・栄養食品協会の「JHFAマーク』認定品です。『JIF Aマーク』とは公益財団法人 日本健康・栄養食品協会が設定した規格基準をクリアーした健康補助食品に許可される安心&安全のマークです。昭和60年に当時の厚生省が設置を認めた財団法人日本健康・食品協会の事業として、健康食品の規格基準の設定及びその基準に係わる認定制度を開始しました。規格成分のみならず、一般細菌や大腸菌なども分し、表示内容についても医学・栄養学の専門家から構成する、認定健康食品認定審査会で審査をし、許可しています。
理由⑤:只今、500円モニター募集中!
今なら、販売18年目のナットウキナーゼのパイオニア「納豆博士」を500円で試すことができるモニターを募集しています。ネットからのお申込み限定で先着300名様となっています。500円で消費税込み価格、しかも送料も無料なので、詳しく知りたい方は、公式ホームページでご確認ください。
【納豆博士】公式ホームページ
![]()









