
アロエは、多くの家庭でも育てられ、観賞用だけではなく、食用にしたり、傷を治すことに利用したりと、多目的な植物として知られています。
アロエは、「医者いらず」と言われているように、多くの有効成分が含まれています。傷を治し易くするだけではなく、いろいろな効能が期待できる、自然界の万能薬なんです!
今回は、知っているようで知らないアロエの歴史や種類、成分やその効果効能をご紹介することで、アロエの秘められたパワーに迫ります!
この記事を読むことでアロエの素晴らしさを知ることができ、アロエが持つ数多くの効果は、きっと、あなたの健康にも役立つ筈です。
アロエサプリのおすすめ人気ランキング5選 を見る
【アロエの歴史】
アロエは大昔から、自然界における健康と美容の万能薬として使われてきました。
クレオパトラは、若さと美貌を保つために、アロエの絞り汁を化粧水として愛用したといわれています。
マケドニア帝国をつくったアレキサンダー大王は、家庭教師役であったアリストテレスの進言により、兵士たちの健康維持のため熱心にアロエを栽培していたそうです。
また、コロンブスは長い航海で乗組員たちの健康を守るために、絶えずアロエを船に積んでいたといわれています。
中国においても973年(唐代)に、開宝本草という医薬書に漢薬名「芦会(ロカイ)」の名で、アロエが記載されていました。
日本においては、鎌倉時代にポルトガルの宣教師によって、アロエが伝来したといわれています。江戸時代にはアロエが漢方薬として用いられていたとの記録が残っています。
現在のように、アロエが健康食品や化粧品として幅広く利用され始めたのは第二次世界大戦の頃からです。アロエの効果が科学的に解明されるにつれて、活用の幅はさらに広がっていきました。
【アロエの種類】
アロエの種類は細分化すると、730種にも及ぶとも言われており、日本国内においても約350種類ほどあるといわれています。その中でも薬効が認められているアロエは、キダチアロエ、アロエベラ、ケープアロエの3種類です。
全てのアロエに効能があるわけではなく、観賞用の種類にはほぼ薬効はないとされています。
◎キダチアロエ
 キダチアロエの「キダチ」の由来は、木の幹から枝が伸びるように茎から葉が広がっていることから、「木が立つアロエ」つまり「キダチアロエ」と呼ばれるようになりました。茎が伸び最大で2m近くまで成長します。
キダチアロエの「キダチ」の由来は、木の幹から枝が伸びるように茎から葉が広がっていることから、「木が立つアロエ」つまり「キダチアロエ」と呼ばれるようになりました。茎が伸び最大で2m近くまで成長します。
寒さに強い品種のため、日本では観賞用としても栽培されています。また、野生にも多く自生し、11月ごろに赤色の花を咲かせます。
キダチアロエは、葉が細くゼリー質の部分は少なく、医薬品として認められてないため、食用として、まるごと全部使えるのが特長です。主に食品や化粧品の原料として利用されています。
キダチアロエは、傷や火傷の外用薬として、また、胃腸薬や便秘薬として内服されるなど古くから生薬として用いられてきました。
◎アロエベラ
 一般的にアロエと呼ばれるものは、この種類を指します。アロエベラのベラ(vera)はラテン語で「真実の」「本当の」という意味です。アロエベラはアメリカやメキシコで多く栽培され、海外ではアロエというとアロエベラのことを指します。
一般的にアロエと呼ばれるものは、この種類を指します。アロエベラのベラ(vera)はラテン語で「真実の」「本当の」という意味です。アロエベラはアメリカやメキシコで多く栽培され、海外ではアロエというとアロエベラのことを指します。
アロエベラは、茎はほとんど無く、肉厚で大きな葉が特徴です。最大で80cm以上になり、葉は、重なるように地面から広がっているため、 横から見ると逆三角形のように広がって見えます。
寒さには弱く、日本では温度管理の整った施設内か、沖縄などの温暖な地域でしか育ちません。「アロエベラ」は、5月ごろに黄色の花を咲かせます。
葉肉の部分に苦みが少なく、主に食用として用いられます。表面の皮をむいて中のゼリー状の果肉部を食べます。
葉のゼリー質は、ヨーグルトやドリンク剤に利用されたり、刺身などの料理にも活用されます。最近では、肌の潤いを保つ働きや肌を引き締める働きがあるとされることから、化粧品などにも使われています。
また、新陳代謝や血行促進、消炎作用、保湿作用、殺菌作用など、多くの薬効があることで知られています。
◎ケープアロエ
 ケープアロエは、南アフリカ共和国ケープ州が原産で、日本では明治13年以来、日本薬局方に健胃や、便秘の医薬品として規定されています。
ケープアロエは、南アフリカ共和国ケープ州が原産で、日本では明治13年以来、日本薬局方に健胃や、便秘の医薬品として規定されています。
このアロエ末が外用の軟膏に処方され、しもやけ、あかぎれ、火傷、切傷などに適用されています。
アロエサプリのおすすめ人気ランキング5選 を見る
【アロエの効果】
アロエはミネラル・ビタミン類をはじめ、高濃度のポリフェノールに代表される抗酸化物質、殺菌作用物質、食物繊維、タンパク質、多糖体など、約200種類もの有効成分が含まれています。それらの有効成分の働きを解明するために、さまざまな研究がなされていると同時に、研究成果は医薬品、サプリメントをはじめ多くの健康食品や民間療法に活用されています。
アロエに期待される主な働き
◎アロエを飲むと・・(内服)
胃・十二指腸潰瘍、胃腸病、肝臓病、解毒作用、気管支炎、粘膜の荒れ、肩こり、血行促進、更年期障害、新陳代謝の活発化、高血圧:血管の弾力化、コレステロールの除去、四十肩・五十肩、基礎体力、乗り物酔い、神経の鎮静効果、胆石・結石、肝機能を高める、低血圧、糖尿病頭痛、脳血管を活性化、頭痛抑制、二日酔い、鼻炎・蓄膿症、粘膜の抗炎症、便秘、抗ガン作用、冷え性、自律神経正常化、体質改善、 喘息、気管支の粘膜保護、細菌の感染防止 、膀胱炎、利尿作用、毒素中和
◎アロエを塗ると・・(外用)
うおのめ・いぼ、 かぶれ・湿疹、殺菌、消炎 、ひび・あかぎれ、患部保護 、火傷、擦り傷・切り傷、化膿を防ぐ、 歯痛・歯槽膿漏、腫れを和らげる、歯茎を引き締める、痔、止血、 打ち身・捻挫、患部の熱を取る、 虫刺され、毒素中和、腫れやかゆみを和らげる
アロエサプリのおすすめ人気ランキング5選 を見る
アロエに含まれる有効成分に関する研究
| 研究成果 | 参照論文 |
| 腸の活動を活性化し炎症を抑える作用。アロエベラゲルの経口摂取で治療が難しい過敏性腸症候群、潰瘍性大腸炎の炎症に対し、アロエベラが症状の改善に有効であることが米国消化器学会で発表されている。過敏性腸症候群患者にとって有望な治療オプションであると思われる。 | 1,11,16,23 |
| 胃壁細胞からの過剰の塩酸の放出を阻害し、胃の炎症を阻害する作用を示した。アロエに含まれるアロクチンAはストレスや絶食時に、胃を保護する働きがあると思われる。 | 10,23 |
| アロエに含まれている、アロエシンとそのエステル類には美白効果があるとされている。 | 23 |
| アロエベラ液汁に保湿成分である加水分解ヒアルロン酸の皮膚浸透を高める効果があるとされている。ヒアルロン酸には、保湿力に優れ肌のハリや弾力を生み出す粘弾性があるとの報告がある。 | 21 |
| アロエジェルは、紫外線などを浴びることによってできる肌のしわや弾力性に対して一定の改善効果がある研究結果が発表されている。抗炎症作用として、紫外線による皮膚の炎症状態の局所治療に有用である可能性についても指摘されてる。シミのもとになるメラニン産生を抑える作用があるとの報告がある。 | 7,13,20 |
| アロエに含まれるアロエニンとアロクチンAとBには抗炎症作用があると思われる。 | 23 |
| アロエベラは抗菌作用、抗ウイルス作用を有し、適切な用法を守ることで怪我の治療、創傷治癒に一定程度有効だと言われている。 | 3,6,12,23 |
| アロエの外用による切り傷、火傷による炎症抗炎症効果は、アロエに含まれるレクチンによるものと推定される。軽度の火傷にアロエベラが治癒効果を持つということを指示する証拠が蓄積されてきている。 | 14,23 |
| アロエに含まれるアセマンナンの投与で早期の口内炎治癒が認められた。 | 23 |
| アロエベラ入り歯磨き粉の使用で歯肉炎や歯垢の大幅な減少が見られたという。アロエベラゲルは、歯の虫歯や歯周病の予防のための消毒剤として使用することで、口腔内の病気を改善する可能性があると結論付けています。 | 2,4,17 |
| アロエが抗炎症作用や子供のおむつ皮膚炎に対する効果について有用である可能性が認められ、おむつ皮膚炎治療の安全で効果的な治療として役立つことを示唆している。 | 8,15 |
| アロエに含まれているアルボランAとBに血糖降下作用があるとされ、アロエベラゲルに非インスリン依存型の糖尿病を抑える効果が期待された。 | 23 |
| 水虫菌(Trichophyton mentagraphytes) に対し抑制効果を示した。 | 23 |
| 日常生活に支障をきたす重度の疲労感が長期間続く状態である慢性疲労症候群に対して、そのリスクを低減させるL-アルギニンの補給効果があるとする研究結果が存在する。 | 18 |
| アロエ成分の服用でアルコール代謝が亢進し、二日酔いの成分となるアセトアルデヒドの分解が促進されたことを示唆している。また、肝線維症患者の線維症と炎症の緩和に役立つ可能性がある。アロエベラゲルは肝細胞において、解毒作用や抗酸化作用を促進していると推定された。 | 5,23 |
| アロエに含まれている、アロエウルシンとアロエマンナンに抗腫瘍効果があるとする研究結果が存在する。 | 23 |
| アロエベラゲルに含まれる成分である、バルバロイン、アロエメオジン、エモジンおよび発酵酪酸塩には、自己免疫疾患の免疫覚醒効果が期待されるとする研究が発表されている。 | 19 |
| 腸内細菌により発酵した酪酸は、高齢者の疾患の予防や老化予防に一定の効果があるとの研究結果がある。 | 22 |
【アロエに含まれている主な栄養成分】
アロエは約200種類もの有効成分が含まれています。主だった成分とその働きを解説します。
アロイン(aloin)
主にアロエの固い表皮部分に多く含まれる苦味成分。日本においては「薬品」と指定され、一般食用のアロエベラ果肉の加工食品には、この成分は含有されていません。大腸に入ると腸を刺激し、腸のせん動運動を活発にし腸管からの水分の分泌を増やす。このことから、便秘の解消効果が期待されます。胃の活動を活発にし、健胃作用があるとされる。過度に摂取するとお腹がゆるくなることがある。硬くなった毛細血管に弾力を取り戻し、血圧を下げる効果がある。殺菌作用も期待できるとされています。過剰摂取により子宮が圧迫されるので、妊婦は摂取に注意が必要。
アルボランA・B(Arboran)
アルボランはアロエに含まれている多糖類で、アロエに含まれる有効成分の一種。インスリンの分泌を促進して血糖値を下げる作用があるとされる。効果は比較的穏やかだが、持続性は高い。糖尿病の治療に用いられているインスリンよりも長期間、持続性が継続するとされる。アルボランにはアルボランAとアルボランBという二種類があり、それぞれ血糖値を引き下げる働きがある。また、新陳代謝を高め、脂肪を燃やす効果がある。
アロエウルシン (Aloe ursin)
アロエウルシンには細胞組織の賦活化作用、組織の再形成促進作用、抗潰瘍作用があるとされる。細胞の再形成を促進する事から外用により火傷の治療作用もあるとされる。胃潰瘍や十二指腸潰瘍の粘膜などに作用し、潰瘍の治りを早める抗腫瘍性、抗炎症、抗潰瘍、殺菌作用がある。また、胃液の分泌を促進する。なお、アロエウルシンはキダチアロエには含有されているが、アロエベラには含まれていない。
アロエエモジン (Aloe-emodin)
アロエエモジンはアロエの皮部分やその内側にあるゼリー状部分に多く含まれる。アロインが体内に入り酸化するとアロエエモジンへ変化する。アロエエモジンは、日本において「薬品」と指定されており、加工食品には、これらの成分は含有されていない。アロエの苦味成分で、解毒作用や、二日酔いに効果があるとされている。胃の活動を活発にすることで胃液の分泌を即し、胃もたれや消化不良を防ぐ。また、腸の活性化作用があるとされ、慢性の便秘に効果があるほか、解毒作用や二日酔いにも効果があると言われている。子宮収縮作用もあるため、妊娠中の摂取には注意が必要。
アロエシン(Aloesin)
アロエシンは、アロエベラおよびキダチアロエの両方に含有されている成分で、シミやそばかすの原因となるチロナーゼ酵素の作用を阻害する事から美白効果があるとされる。また、殺菌効果や抗菌作用もあるとされる。
アロエソンエモジン(Aloeson emodin)
健胃作用・緩下作用
アロエチン(Aloetin)
アロエチンはアロエに含まれる有効成分の一つ。苦みはほとんどない。高い殺菌力と解毒作用、抗カビ作用、抗炎症作用があるとされている。外用により化膿や吹き出物といった皮膚症状の治療、内服により腸内環境の正常化や、風邪、肝臓病などに対しても効果があるとされる。その他、メラニン色素の沈着を防ぐ効果もあり、シミやそばかすの予防による美白効果も期待されている。アロエベラおよびキダチアロエの両方に含有されている。
アロエニン(Aloenin)
アロエニンは、主にキダチアロエのみに含まれるアロエの有効成分で、胃酸の働きを正常化する作用があるとされる。胃酸過多の際は胃酸の分泌を抑え、胃酸不足のときは胃酸の分泌を促進する作用がある。
アロエボラン(Aloe Boran)
血糖値を下げる働きがある。新陳代謝を促進し余分な脂肪を燃やすことで肥満の改善・予防に力を発揮します。
アロエマンナン (Aloe mannan)
アロエマンナンは、アロエに含有されている多糖類の一つで、皮膚の老化防止作用、血行を促進する作用や抗腫瘍作用などがあるとされる。アロエの果肉部分に含まれておりネバネバとした果汁の原因物質である。
アロクチンA・B (Aloctin A・B)
抗腫瘍効果、抗炎症効果、胃病変の抑制、抗ガン作用があるとされる。
アロミチン(Aromitine)
アロミチンは、ウイルスの活動を抑えるという抗ウイルス作用や抗腫瘍作用があるとされる成分。また、免疫を増強させる効果があると言われており、粘膜を弾力化し老廃物を排泄する 。抗腫瘍性、抗潰瘍作用、抗がん・抗ウイルス作用もあるとされている。アロミチンは、ダチアロエ、アロエベラの双方に含まれている。
アントラキノン (Anthraquinone)
天然のアントラキノン誘導体は下剤として働くものが多いとされている。
サポニン(saponin)
サポニンは、アロエに含まれているえぐ味の原因となる成分で、血中コレステロールや中性脂肪を減少させる作用や、動脈硬化の予防にも効果があるとされる。また、脂質の合成、吸収の阻害作用があることからダイエット効果も期待される。血糖値の上昇を抑え血液の流れを良くする。心筋梗塞、脳梗塞の予防にも役立つ。また、利尿作用を促進し、むくみを防止する。中長期の服用は腸管の組織を活性化させることにから肥満体質の改善に効果的とされている。また、アレルギー体質の改善作用や去痰作用もあるとして現在研究が進められている。
サルチル酸(Salicylic acid)
サリチル酸は、植物ホルモンの一種。消炎鎮痛作用、皮膚の角質軟化作用、消炎鎮痛作用がある。
タンニン酸(Tannic acid)
タンニン酸は、ポリフェノールの一種で強い渋みが特徴。肌への塗布により、毛穴を引き締める効果があり、化粧品などに配合されている。腸粘膜表面のタンパク質と結合して不溶性の被膜を形成する。粘膜の保護作用、炎症抑制作用を示す。また、抗酸化力を持つことから、動脈硬化を防ぎ、生活習慣病予防にも効果を示す。
バルバロイン(Barbaloin)
アロインを構成する成分のうち、もっとも含量が高いのがバルバロインである。苦味の成分。少量では健胃作用、大量では大腸を刺激して瀉下作用を起こす。健胃薬、瀉下・緩下薬として用いられる。
ビタミン類(Vitamins)
ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB3、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンE、葉酸
ミネラル(mineral)
アロエに含まれるミネラルで代表的なものとしてカルシウム、カリウム、鉄分、亜鉛、銅、マグネシウムなどが挙げられる。ミネラルが不足すると体内では様々な欠乏症が現れる。メラニン形成阻害作用(美肌効果)シミ・そばかすの緩和(美白効果)が期待される。
アミノ酸・有機酸(amino acid)
アミノ酸は、体内において様々なタンパク質や神経伝達物質を生成する上で必要不可欠な存在である。体内で合成できないアミノ酸を必須アミノ酸と呼ぶ。アロエに含まれる主なアミノ酸にはバリン、ロイシン、イソロイジン、トリプトファン、リジン、アラニン、フェニルアラニン、チロシン、ヒスチジン、アルギニン、ヒドロキシプロリン、アスパラギン酸、グルタミン酸、プロリン、シスチン、グリセリン、メチオキン、セリンなどがある。
ムコ多糖類(Mucopolysaccharide)
ムコ多糖類は、アロエベラの葉の中に含まれている成分で、細胞と細胞を結合するゲル状の物質です。ムコ多糖類は保水性に優れ、人の体内の関節や皮膚など、いたるところに存在している。肌の健康や関節痛の緩和などの作用がある。また、コレステロール値を低下させる作用も期待できる。ムコ多糖類は、火傷や日焼けなどで傷ついた皮膚の炎症を抑えるとともに、皮膚の組織を修復する。また、免疫を向上させる効果もあるとされる。ムコ多糖類の作用として、アロエベラなどを塗ると、しっとりして肌に潤いを与える効果がある。また、血液をサラサラにするといった効果も期待されている。アロエに含まれる主なムコ多糖類には、グルコース、フルクトース、アラビノース、キシロース、マンノース、ガラクトース、セルロース、ウロン酸、尿酸、ラムノース、グリコーゲン、アルドネントースがある。
酵素類
酵素は、体内に摂取した食べ物を消化・吸収・代謝する際に手助けをしてくれる重要な栄養素です。
アロエに含まれている主な酵素
アミラーゼ、アリナーゼ、アルドナターゼ、アンチトリプシン中和物質、オキシターゼ、オクシトーゼ、カタラーゼ、セルラーゼ、セルロース、トリプシン様プロテアーゼ、マノーゼ、ラモノーゼ、リパーゼ
アロエサプリのおすすめ人気ランキング5選 を見る
【アロエを利用する際の注意点】
最近では、アロエベラの生葉が小売店の店頭や、通信販売などでも流通しています。
健康によいというアロエですが、適切な摂取量や使用する際の注意点も確認しより安全に活用し健康に役立てましょう。
◎摂取量の目安
アロエの摂取目安量は、アロエベラの場合であれば、一日60g、キダチアロエが15gほどとされています。しかし、アロエを普段から食べ慣れておらず、初めてアロエを食生活に取り入れようという方は、10〜20gほどの少量から始めるのがよいでしょう。アロエは食べ過ぎてしまうと、お腹がゆるくなることがあるので、あくまで適度な量にとどめましょう。
アロエを妊娠中の人が食べる場合、アロエに含まれるアロインという成分が、影響を及ぼすことがあるので注意が必要です。
アロインには子宮を収縮させる作用があります。そのため妊婦はアロエの過剰摂取に気を配る必要があり、食べる量を控えめにするのがおすすめです。また、一般の方に関しても、食べ過ぎには注意が必要で、適量の摂取を心がけてください。
アロエにはたくさんの非常に優れた作用があります。しかし、アロエはあくまで健康を補助してくれるものという考えで使うのがよいと思います。
健康に不安がある際には、まずはお医者様に診てもらうようにしましょう。
また、今は、アロエの優れた成分を利用した、とても素晴らしいサプリメントや健康食品も、数多く販売されています。
それらを有効に活用して効率的にアロエの効果を毎日の生活に取り入れることも、お勧めいたします。
是非、あなたの毎日の生活習慣に、アロエを取り入れてみませんか?
アロエサプリのおすすめ人気ランキング5選 を見る
【参考文献】
(1) A Pilot Study of the Effect of Aloe Barbadensis Mill. Extract (AVH200®) in Patients With Irritable Bowel Syndrome: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26405698/ (2) Aloe Vera in the Treatment for Oral Submucous Fibrosis – A Preliminary Study https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22650317/ (3) A Comparative Study of the Effects of Topical Application of Aloe Vera, Thyroid Hormone and Silver Sulfadiazine on Skin Wounds in Wistar Rats https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22474470/ (4)Inhibitory Activity of Aloe Vera Gel on Some Clinically Isolated Cariogenic and Periodontopathic Bacteria https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22466882/ (5) Antifibrotic Effect of Aloe Vera in Viral Infection-Induced Hepatic Periportal Fibrosis https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22563189/ (6) Final Report on the Safety Assessment of AloeAndongensis Extract, Aloe Andongensis Leaf Juice,aloe Arborescens Leaf Extract, Aloe Arborescens Leaf Juice, Aloe Arborescens Leaf Protoplasts, Aloe Barbadensis Flower Extract, Aloe Barbadensis Leaf, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice,aloe Barbadensis Leaf Polysaccharides, Aloe Barbadensis Leaf Water, Aloe Ferox Leaf Extract, Aloe Ferox Leaf Juice, and Aloe Ferox Leaf Juice Extract https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17613130/ (7) Melanogenesis and Antityrosinase Activity of Selected South African Plants https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22611429/ (8) A Randomized Comparative Trial on the Therapeutic Efficacy of Topical Aloe Vera and Calendula Officinalis on Diaper Dermatitis in Children https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22606064/ (9) Preliminary Evaluation: The Effects of Aloe Ferox Miller and Aloe Arborescens Miller on Wound Healin https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18773950/ (10) Effects of Aloe Extracts, Aloctin A, on Gastric Secretion and on Experimental Gastric Lesions in Rats https://ci.nii.ac.jp/naid/110003649897 (11)A Pilot Study of the Effect of Aloe Barbadensis Mill. Extract (AVH200®) in Patients With Irritable Bowel Syndrome: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26405698/ (12)Effect of the Combination of Aloe Vera, Nitroglycerin, and L-NAME on Wound Healing in the Rat Excisional Mode https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9395704/ (13)Investigation of the Anti-Inflammatory Potential of Aloe Vera Gel (97.5%) in the Ultraviolet Erythema Test https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18253066/ (14)The Efficacy of Aloe Vera Used for Burn Wound Healing: A Systematic Review https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17499928/ (15)A Randomized Comparative Trial on the Therapeutic Efficacy of Topical Aloe Vera and Calendula Officinalis on Diaper Dermatitis in Children https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22606064/ (16)Randomized, double‐blind, placebo‐controlled trial of oral aloe vera gel for active ulcerative colitis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1365-2036.2004.01902.x (17)Effect of a dentifrice containing aloe vera on plaque and gingivitis control. A double-blind clinical study in humans https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-77572008000400012&lng=en&tlng=en (18)[慢性疲労症候群に対するL-アルギニンによるアロエベラジュースの推定予防 (Vol 5, No 2 1950-1956 ed.). 消化器肝臓学会誌. (2016)] (19)Prophylactic aloe components on autoimmune diseases: barbaloin, aloe-emodin, emodin, and fermented butyratehttp://www.ghrnet.org/index.php/joghr/article/view/2283(20)Dietary Aloe Vera Supplementation Improves Facial Wrinkles and Elasticity and It Increases the Type I Procollagen Gene Expression in Human Skin in vivo.
http://www.fih.jp/thesis/A00600.html (21)「美肌効果の解明が進むアロエベラ液汁 新たに加水分解ヒアルロン酸の皮膚浸透を高める効果を発見」 https://www.kobayashi.co.jp/corporate/news/2017/170316_02/index.html(22)Possible Prophylaxes of Aloe Vera Gel Ingestion to Butyrate Metabolism http://www.ghrnet.org/index.php/joghr/article/view/1892 (23)Bioactive ingredients of Aloe : a review update,2020 https://japan-aloe.org/wp-content/uploads/aloe-ingredient_2002.pdf


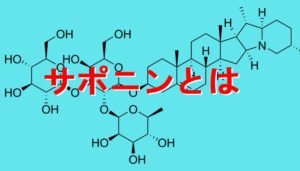



 キダチアロエの「キダチ」の由来は、木の幹から枝が伸びるように茎から葉が広がっていることから、「木が立つアロエ」つまり「キダチアロエ」と呼ばれるようになりました。茎が伸び最大で2m近くまで成長します。
キダチアロエの「キダチ」の由来は、木の幹から枝が伸びるように茎から葉が広がっていることから、「木が立つアロエ」つまり「キダチアロエ」と呼ばれるようになりました。茎が伸び最大で2m近くまで成長します。 一般的にアロエと呼ばれるものは、この種類を指します。アロエベラのベラ(vera)はラテン語で「真実の」「本当の」という意味です。アロエベラはアメリカやメキシコで多く栽培され、海外ではアロエというとアロエベラのことを指します。
一般的にアロエと呼ばれるものは、この種類を指します。アロエベラのベラ(vera)はラテン語で「真実の」「本当の」という意味です。アロエベラはアメリカやメキシコで多く栽培され、海外ではアロエというとアロエベラのことを指します。 ケープアロエは、南アフリカ共和国ケープ州が原産で、日本では明治13年以来、日本薬局方に健胃や、便秘の医薬品として規定されていま
ケープアロエは、南アフリカ共和国ケープ州が原産で、日本では明治13年以来、日本薬局方に健胃や、便秘の医薬品として規定されていま


