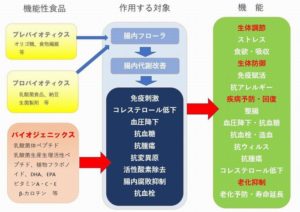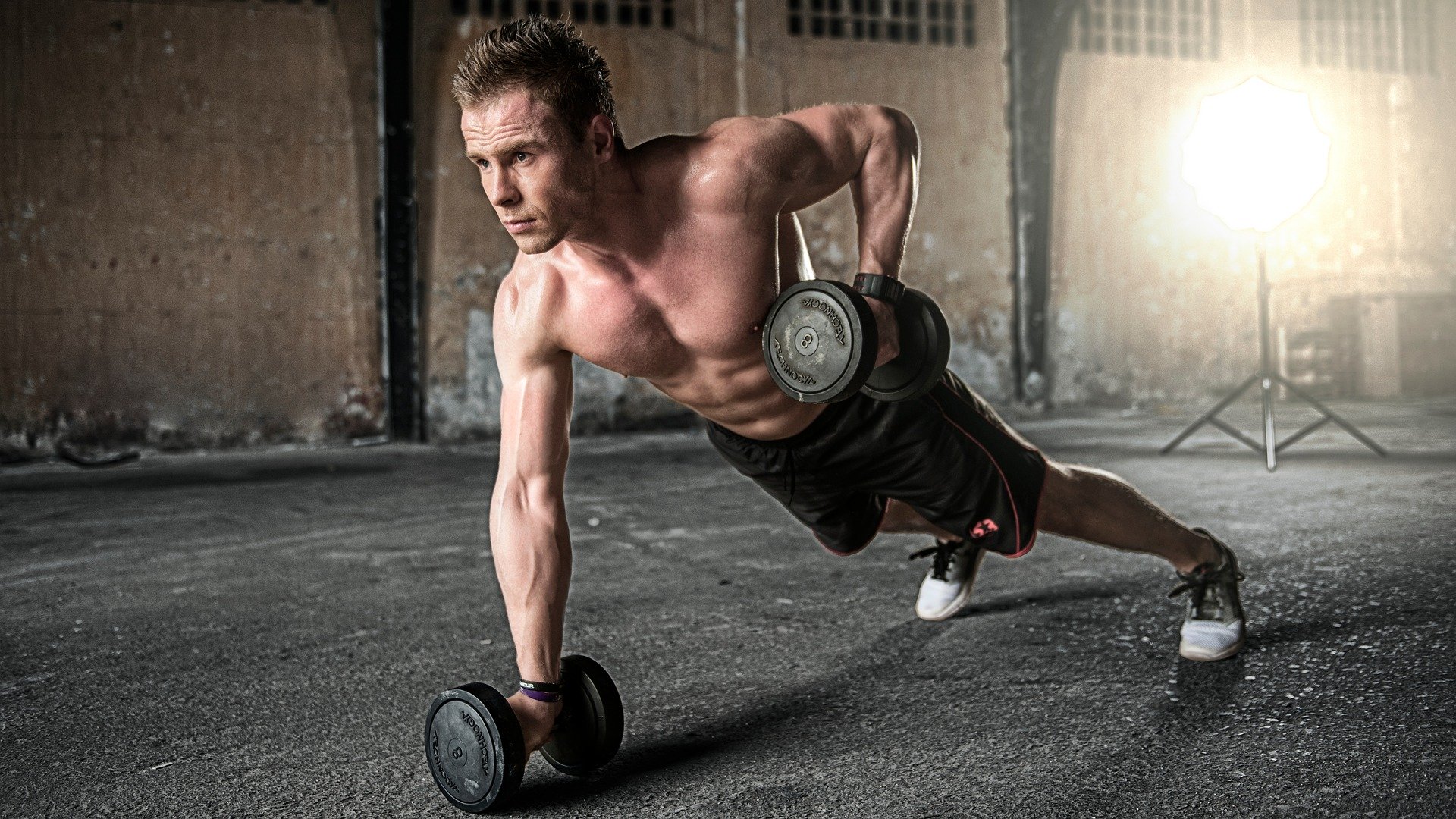疲れやすくなった
慢性的に肩こりが続く
手や足が、むくみやすい
すぐにイライラしたり落ち込んだり、些細なことで、怒りっぽくなったり…
なんとなく体調が悪すぐれない・・・
病院の検査では何も異常がないけれど、やっぱり体の調子がおかしい・・・
このように「健康」と「病気」の間にある状態を、東洋医学では「未病」といいます。
実際、健康と病気の間には、明確な境界線がある訳ではなく、体は健康な状態から長い期間もかけて少しづつ変化していくのです。油断をして疲れが溜まったままの状態にしていると、後戻りできないことになってしまうかもしれません。
大切なことは、できるだけ早いうちに気づき、対策を実行することです。
不規則な生活による疲労やストレスによって自律神経の働きが乱れると、体の器官にさまざまな不調が現われやすくなります。
自律神経は、身体の活動を調整するために、24時間働き続けている神経です。体の活動時や昼間に活発になる交感神経と、安静時や夜に活発になる副交感神経があり、その2つのバランスをそこなうと様々な不調を感じます。
耳鳴り、頭痛、倦怠感、易疲労感、ドライアイ、涙目、胃腸の不快感、食欲不振、便秘、下痢
めまい、不眠、寝付きの悪さ、手足の震え、しびれ、喉の不快感、つまり感、動悸、息苦しさ
不安感、イライラ、落ち込み
おススメの「ローヤルゼリーサプリメント」はこちら
自律神経の働きにダメージを与える原因
自律神経は精神的および肉体的なストレスでバランスを崩したり、うまく働かなくなります。ストレスに対する耐性の強さは人それぞれです。少しのことで乱れる人もいれば、ある程度、強いダメージにも耐えられる人もいます。しかし、どれだけストレスに強いと思っている人であっても許容範囲をを超えてしまえば同じようにその働きがば乱れてしまいます。
そこで、注目したいこの成分
ストレスや疲れからくる自律神経の乱れを、自分一人の力ででコントロールするのは容易なことではありません。そこで、注目したいのが「ローヤルゼリー」です。なぜ、自律神経の乱れにローヤルゼリーなのでしょうか。それには、理由があります。誰もが、「ローヤルゼリー」という名前は聞いたことがあると思います。それでは、ローヤルゼリーはどのようにできるのか、また、どのような成分が含まれ、そして、その成分がどのような働きを持っているのか、ご存じででしょうか?
ローヤルゼリーのパワー
ローヤルゼリーは、羽化して6日~12日間の若い働き蜂が花粉や蜂蜜を食べ、体内で消化吸収した後に体内で合成し、分泌する乳白色のクリーム状の物質です。なので、ローヤルゼリーは、花の蜜が主原料であるハチミツとは全く違うものなのです。ローヤルゼリーは、女王蜂となる幼虫のみに与えられる食物です。女王蜂が、他の働きバチに比べ長寿で体も大きくなるのは、まさに、このローヤルゼリーのおかげです。ローヤルゼリーには、他の物質には含まれていない有用な栄養素が豊富に含まれています。
ミツバチは、卵の段階では、働き蜂も女王蜂も同じ蜂です。ところが、生涯にわたり栄養価の高いローヤルゼリーを食べ続ける女王蜂の体の大きさは、働き蜂と比べて2〜3倍、寿命は30〜40倍にもなるのです。また、卵を産むことができないメスの働き蜂に対して、女王蜂は毎日約1,500個もの卵を産み続けることができるなど、その能力は圧倒的に異なります。まさにこの女王蜂の超越した生命力を育てる源こそが、ローヤルゼリーなのです。
ローヤルゼリーに含まれる栄養素
ローヤルゼリーには、ビタミンB類、リジン、メチオニン、スレオニンといったアミノ酸、ロイヤリシン、ロイヤラクチン、アピシンなどのタンパク質、デセン酸に代表される脂肪酸、また、多くのミネラルや葉酸、植物ステロール、酵素、抗菌物質、ビタミンCなど、豊富な栄養素が含まれています。ローヤルゼリーのタンパク質は、必須アミノ酸の含有バランス品質を示すアミノ酸スコアが100で、鶏卵と同スコアであり、良質なタンパク質といえます。そのほかにもローヤルゼリーには50種類以上の多彩な成分が含まれています。
おススメの「ローヤルゼリーサプリメント」はこちら
自律神経を整える2つの成分
ローヤルゼリーには、「アセチルコリン」と「デセン酸」とい2つの自律神経を整える働きを持った成分が含まれています。
デセン酸
ローヤルゼリーは、近年、特に科学的な研究が進められ、自然界ではローヤルゼリーのみに存在する「デセン酸」という物質が大量に含まれていることが分かりました。
デセン酸とは、正式名称を「10-ヒドロキシデセン酸」といい脂肪酸の一種です。
デセン酸はインスリンと同じような働きも持っていて、体内の糖代謝を正常にする働きがあることが知られています。体内の血糖値を低下させることで、インスリンの働きが悪くなって起こる糖尿病の予防に役立つことが期待されています。
また、自律神経失調症や女性ホルモンのバランスの乱れから起こる、更年期障害に有効であるといわれています。また、デセン酸は、女性ホルモンであるエストロゲンによく似た働きをもつことから、美肌、美髪効果や、血行を促進するといった働きが期待できます。また、コレステロール値、血圧の改善にも役立つことから、男性にも、ローヤルゼリーが選ばれる理由となっています。
アセチルコリン
ローヤルゼリーには、アセチルコリンという物質が豊富にふくまれています。アセチルコリンは、副交感神経や運動神経の末端から放出される神経伝達物質です。自律神経のうち、副交感神経を刺激し、脈拍を安定させたり、自律神経をコントロールする上で最も大切である間脳を正常に保つ働きをします。間脳には、自律神経のバランスを調節する視床下部という、生命活動のコントロールする部位があり、この間脳の働きが衰えてくると、いわゆる更年期障害や、自律神経失調症を起こしてしまいます。アセチルコリンは、その働きを活性化する物質なのです。
また、脳にある神経細胞は、シナプスと呼ばれる組織で結合しあい、アセチルコリンによて、情報を伝達したり記憶したりするのです。アセチルコリンが少なくなると、記憶力の低下や物忘れの原因に野なってしまうのです。
おススメの「ローヤルゼリーサプリメント」はこちら
他にもあるローヤルゼリーの効能
秘めたパワーを持つローヤルゼリーは世界中の研究機関によって日々、研究されており、新たな効能が発見されています。
免疫調節効果
ローヤルゼリーはバセドウ病に対する免疫調節剤となる可能性が報告されています[1]。また、脳のグリア細胞[2]や神経幹細胞の成長を刺激することも報告されている[3]。これまでに、ローヤルゼリーが抗炎症、外傷治癒、抗菌作用があるという報告があります。
冷え症
女性を対象とした試験によって、ローヤルゼリーには冷え症改善効果があることが示されました。実際に、20℃の冷水に1分間手を浸し、体温の回復をサーモグラフィーにより解析した結果、ローヤルゼリーを、1日に2.8グラム、2週間摂取した冷え症の方の体温回復が早まることが明らかになっています[4]。
肩こり
40〜59歳の肩こり症状を自覚している健康な女性33名を対象とした試験において、ローヤルゼリー摂取による肩こり症状の軽減効果が研究発表されています。ローヤルゼリー1200 mgを4週間継続摂取し、肩こりの自覚症状と肩表面の血流と、筋肉の硬度の変化を調べた結果、ローヤルゼリーを摂取した人の首筋のはりをやわらげ、肩こりの改善に効果があることが示されました[5]。
耳鳴り
軽度の耳鳴り患者を対象とした臨床試験によって、ローヤルゼリー摂取による軽度の耳鳴り症状が軽減されることが明らかとなっています。試験では、1日2.8 gのローヤルゼリーを8週間継続飲用したところ、ローヤルゼリーを少量しか摂取しなかったときよりも耳鳴り症状が軽減することが示されています[6]。
血圧改善作用
ローヤルゼリーの血圧改善作用を調べるため、血圧が高めもしくはやや高い30〜40歳代の男女にローヤルゼリーを毎日4週間食べてもらい、血圧、脈拍、体重、血液などの変化を調べた。結果は、最も多くののローヤルゼリーを食べたグループは、血圧が低下し、改善したことが示されました[7]。
骨密度への作用
女性ホルモンの減少によって起きる骨粗鬆症に対するローヤルゼリーの作用を調べるため、骨粗しょう症の予防効果を調べた。実験の結果、ローヤルゼリーを摂取は、骨密度の減少が抑えられ、骨粗しょう症予防に効果があることが示された。ローヤルゼリーは小腸でのカルシウム吸収を盛んにすることで、骨粗しょう症を予防する可能性も示されている[8]。
インスリン抵抗性に対する作用
糖尿病の初期症状の一つであるインスリン抵抗性試験によって、ローヤルゼリーによる血糖値を下げるインスリンが働きにくくなる状態の改善効果が明らかとなっています[9][10]。
筋力に対する作用
ローヤルゼリーを摂取すると、筋肉量の増加が見られ、その作用は、ローヤルゼリー投与量に依存して増加したとの報告がある。また、筋肉の損傷においても、ローヤルゼリーは筋肉細胞の増殖を促し、加齢による筋肉の衰えを軽減する可能性が示されています[11]。
不定愁訴
ローヤルゼリーを摂取した結果、頭重、倦怠感、食欲不振、無気力などの不定期愁訴の改善にきわめて有効であると報告されています[12]。
コレステロールとの関連
ローヤルゼリーの摂取により血清中のコレステロールのレベルが減少し、心臓や血管の病気のリスクが低減したと報告されています[13][14]。
抑うつとの関連
ローヤルゼリーを摂取すると、ストレスによる精神的疲労(無気力)の改善に有効でるとの報告があります[15]。
抗菌活性
ローヤルゼリーの抗菌活性を測定したところ、新鮮であるほど抗菌活性が高いことが示された。また、抗菌活性成分を探索したところ、デセン酸であることが判明した[16]。
肥満防止効果
ローヤルゼリーの抗肥満効果と、抗アレルギー作用、アレルギー反応抑制作用が報告されています[17]。
このように自律神経のサポートなど、ローヤルゼリーは、とても多くの有益な働きを持っています。しかし、万能ともいえるローヤルゼリーも、通常の食生活だけでは摂取することができません。そこでローヤルゼリーを配合したサプリメントを利用することになります。現在、ローヤルゼリーサプリメントは、とても数多くの商品が販売されています。その中で何を基準に選んだら良いのか迷ってしまうのではないでしょうか。
おススメの「ローヤルゼリーサプリメント」はこちら
ローヤルゼリーの選び方
品質の良いローヤルゼリーサプリメントを選ぶにはいくつかのポイントがあります。
・値段の安さでは選ばない
・長く商品を作り続けている信頼ある製造メーカーを選ぶ。
・安全性などの品質を確保するための厳しい基準で製造されている商品を選ぶ
・購買リピート率の高い信頼されている商品を選ぶ
・有効成分が豊富に含まれている商品を選ぶ
・飲みやすい形状になった商品を選ぶ
天然のローヤルゼリーを濾過し、不純物を取り除いただけのローヤルゼリーは、品質がとても不安定になります。空気に触れたり熱を加えたりするだけで、簡単に成分が劣化してしまいます。またローヤルゼリーには、ピリッとした独特の酸味があり、製品によっては、毎日飲み続けるのが辛いという方も。いくら素晴らしい効果を持ったローヤルゼリーであっても、一定期間は継続して利用することが重要です。そのためにも、これらの条件をクリアした商品を選ぶことが大切です。
自律神経の働きが弱っていたり、体力が落ち気味の方の栄養補助に、また、今まで不足しがちだった栄養素を補い、毎日をよりハツラツと過ごしたい方のために、ローヤルゼリーサプリメントを上手く取り入れてみましょう。
おススメの「ローヤルゼリーサプリメント」はこちら

【参考文献】
[1]Erem C, Deger O, Ovali E, Barlak Y (2006). “The effects of royal jelly on autoimmunity in Graves’ disease”. Endocrine 30 (2): 175-183.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17322576/
[2]Hashimoto, M.; Kanda, M.; Ikeno, K.; Hayashi, Y.; Nakamura, T.; Ogawa, Y.; Fukumitsu, H.; Nomoto, H. et al. (April 2005). “Oral administration of royal jelly facilitates mRNA expression of glial cell line-derived neurotrophic factor and neurofilament H in the hippocampus of the adult mouse brain”
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1271/bbb.69.800
[3] Hattori, N.; Nomoto, H.; Fukumitsu, H.; Mishima, S.; Furukawa, S. (October 2007). “Royal jelly and its unique fatty acid, 10-hydroxy-trans-2-decenoic acid, promote neurogenesis by neural stem/progenitor cells in vitro”
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18000339/
[4] Guo H, Saiga A, Sato M, Miyazawa I, Shibata M, Takahata Y, Morimatsu F (2007). “Royal jelly supplementation improves lipoprotein metabolism in humans”
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17934240/
[5] 立藤智基、浅間孝志、土井志真、菅野智子、橋本健,“肩こり症状に対するローヤルゼリー含有食品の改善作用-プラセボ対照二重盲検試験による検討―”
[6] 嶽良博、奥野吉昭、沖原清司、橋本健、榎本雅夫,“ローヤルゼリー含有食品による耳鳴症状の改善効果の検討試験”
[7] 梶本修身, 中妻章, 土井志真, 西村明, 梶本佳孝, 平田洋, “ローヤルゼリータンパク質加水分解物の正常高値血圧者および軽症高血圧者に対する降圧作用の検討”
[8] Hidaka S, Okamoto Y, Uchiyama S, Nakatsuma A, Hashimoto K, Ohnishi ST, Yamaguchi M (2006). “Royal jelly prevents osteoporosis in rats: beneficial effects in ovariectomy model and in bone tissue culture model”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1513150/
[9] Nomura M, Maruo N, Zamami Y, Takatori S, Doi S, Kawasaki H (2007). “Effect of long-term treatment with royal jelly on insulin resistance in Otsuka Long-Evans Tokushima Fatty (OLETF) rats”.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17978564/
[10] Zamami Y, Takatori S, Goda M, Koyama T, Iwatani Y, Jin X, Takai-Doi S, Kawasaki H (2008). “Royal jelly ameliorates insulin resistance in fructose-drinking rats”
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18981581/
[11] 牛凱軍、郭輝、崔宇飛、小林順敏、永富良一. “ローヤルゼリーの高齢マウスの筋衛星細胞の機能と増殖能への影響”,
[12]高須靖夫, 太田喜昭, “内科領域におけるローヤルゼリー散の臨床効果”, 診断と新薬
[13] Vittek J. (1995). “Effect of royal jelly on serum lipids in experimental animals and humans with atherosclerosis”
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7556573/
[14] Guo H, Saiga A, Sato M, Miyazawa I, Shibata M, Takahata Y, Morimatsu F (2007). “Royal jelly supplementation improves lipoprotein metabolism in humans”
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17934240/
[15] 池田勇五、鷲塚昌隆、古市浩康、福田陽一、桑原優, “ストレスとローヤルゼリー”
[16] 八並一寿、越後多嘉志, “蜂蜜およびローヤル・ゼリーの抗菌作用”
[17] 蒲原聖可『サプリメント事典』