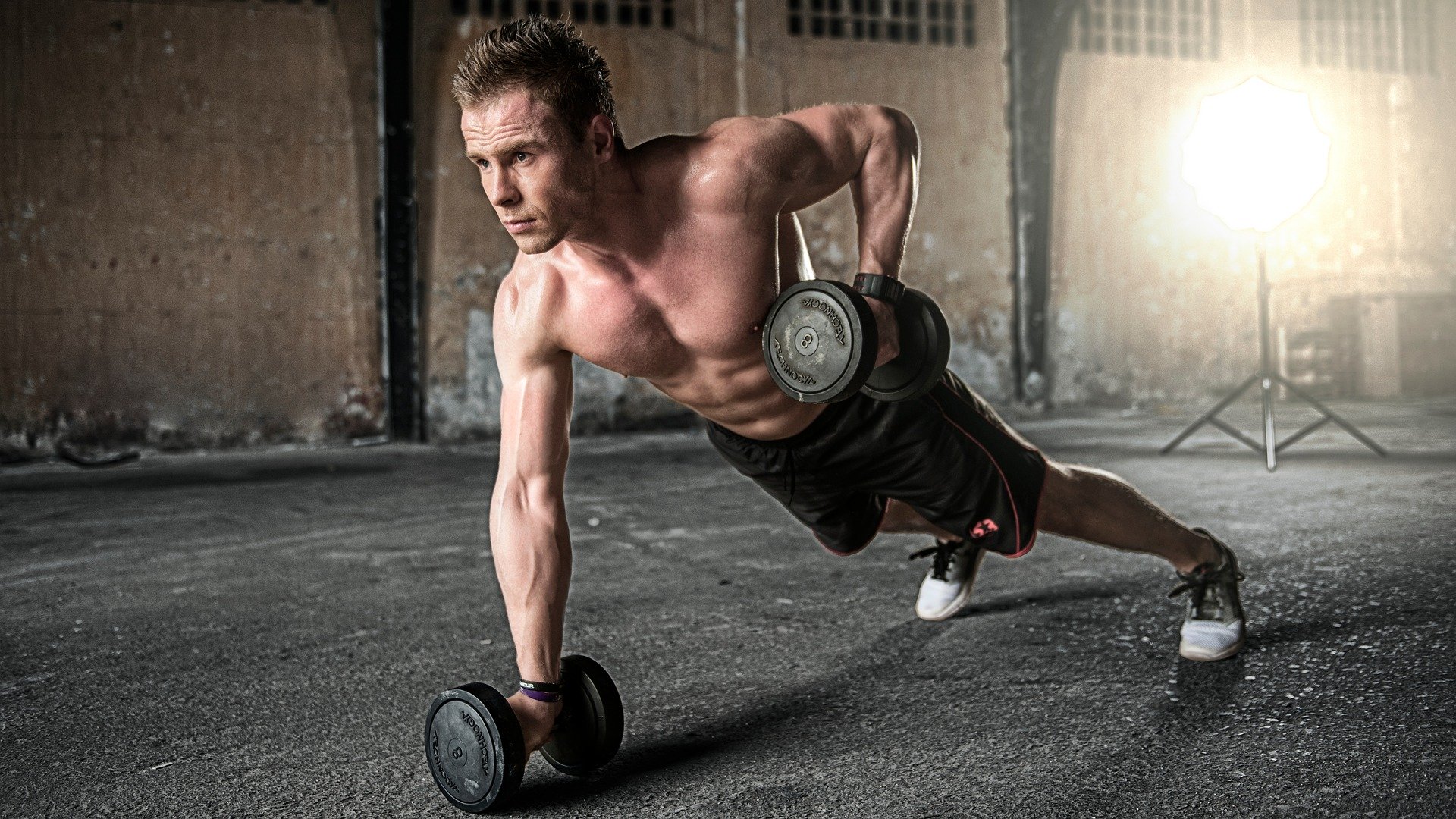タンパク質(プロテイン)とは
プロテインと聞くと多くの人は、
「ムキムキの筋肉作りというイメージ」
「運動している人がとるサプリメント」
といったイメージを想像するかもしれません。
今回は、よく耳にするけど、分からないことも多い「タンパク質」について解説いたしします。
タンパク質の働き
タンパク質は、六大栄養素の一つで、身体の中で筋肉や皮膚、血液、臓器や細胞の主要な構成成分で、生命の維持に欠くことのできない栄養素です。体内のタンパク質は、約20種類のアミノ酸がさまざまな組み合わせで結合することにより作られています。人体には約10万種類のタンパク質が存在しているといわれています。また、筋肉のエネルギー源にもなるため、スポーツサプリメントとしても注目されています。
そのようなタンパク質には次の5つの役割があります。
①生体の構成成分となる
毛髪や爪、皮膚、筋肉、血液、臓器など体を構成
する細胞の主成分であり、水分を除くと体内に最も多く存在する物質でもある。
②酵素となる
体内の化学反応を触媒する酵素もタンパク質からつくられている。
③ホルモンの材料となる
たんぱく質は各種のホルモンとなってカラダを維持・調節しています。
④免疫反応にかかわる
体内に侵入した異物(主にウイルス)を撃退する最も重要な細胞であるキラーT細胞は、良質なたんぱく質をとることで、大量につくりだすことができます。
⑤エネルギー源となる
糖質や脂質と同様、エネルギー源としても使われており、1グラム当たり4kcalのエネルギーを産生しています。
植物や細菌はアミノ酸を自らの体内で合成し、必要なタンパク質をつくっています。ところが、私たち人間は、新陳代謝を繰り返していくために必要とされている、すべてのアミノ酸を自分の体内で合成することができないのです。つまり、私たちは必要なタンパク質を食物から摂取しなければなりません。
タンパク質の摂取方法
タンパク質は基本的に毎日、補給する必要があります。タンパク質を効率よく摂取するには、良質なタンパク質を含んだ食品をバランスよく摂ることが重要になります。必須アミノ酸を豊富に含む動物性タンパク質に加えて、穀物や豆類など血中のコレステロール値を低下させる効果が期待できる植物性タンパク質も体の機能を高めるためには必要です。タンパク質の過剰摂取で健康を損なってしまったというような報告はありませんが、極端な過剰摂取は、内臓疲労や、カロリーオーバー、腸内環境に悪影響を及ぼす可能性があります。体内の過剰なタンパク質は分解されて体外に排出されてしまいますが、やはりバランスのよい適量の摂取を心がけましょう。
タンパク質が体内で代謝される際には、ビタミンB6が 関与します。動物性タンパク質を多く摂る場合には、ビタミンB6も多く摂ることを心がけてください。
タンパク質の摂取量が多いと、尿中のカルシウム排泄量が増大します。これはタンパク質に含まれる硫黄(イオウ)やリンが代謝されることによって作られた硫酸やリン酸を中和するために、カルシウムが消費されるからです。カルシウムの補給にも十分配慮したいところです。
また、肉類からタンパク質を摂るときは、脂肪も存在していることが多いので注意が必要です。一方で、タンパク質の摂取が不足すると、免疫力の低下などさまざまな弊害を招く可能性があります。高齢者が積極的にタンパク質を摂ることによって、加齢による筋肉の減少を補うこともできます。タンパク質を構成するアミノ酸の一つであるグリシンを摂取すると、翌朝の目覚めがすっきりし、疲労感も軽くなるという報告もあります。アミノ酸は持久力の向上や、筋肉痛、疲労の軽減など重要な役割を果たすといわれているので、スポーツをする時にも積極的に摂取したい栄養素です。
タンパク質の食事摂取基準(推奨量)
タンパク質の摂取量は、厚生労働省が、制定した栄養素の摂取基準である食事摂取基準において、次のように記載されています。
成人男姓 60g/日
成人女性 50g/日
これは、基準値なので、運動量やライフスタイルによって、アレンジすることも必要かと思います。
欠乏症と過剰症
タンパク質が身体に不足すると、短期間の欠乏では、全身の筋肉が衰えて、血管がもろくなり、抵抗力が低下しやすくなります。また、血液の成分であるヘモグロビンが不足し、鉄欠乏性貧血を起こすこともあります。長期間の欠乏の場合は発育障害を招く恐れも考えられます。
まとめ
【タンパク質の役割】
①生体の構成成分となる
②酵素の材料となる
③ホルモンの材料となる
④免疫反応にかかわる
⑤エネルギー源となる
【タンパク質の摂取方法】
タンパク質は本的に毎日、補給する必要があります。
ビタミンB6やカルシウムも併せて摂りましょう。
【一日の基本摂取量】
成人男姓 60g/日
成人女性 50g/日